■
「いきどほり」と融合した「さびしさ」という情念を軸にすえた、折口信夫が一生かけて探求した問題の解明■
学者・折口信夫は、歌人・釋迢空の名において、次のような歌を詠んでいる。
いきどほる心すべなし。
手にすゑて、 蟹のはさみを もぎはなちたり
自らの生の根底に、「怒り」や「いきどほり」といった情念を抱えていた折口信夫。しかし、激情しての「怒り」は、他者とのあいだで共感を作り出さない限り、世間からは受け入れられない、孤独な怒りに終わってしまう。そこに残るのは一人感じる「さびしさ」という諦念に近い感情である。
著者は、
「いきどほり」と融合した「さびしさ」という情念を軸にすえて、折口信夫が一生かけて探求した問題について解明を試みている。それは、日本の「神」とはいったいどのようなものなのか、という問いである。
宗教的熱情を根底にもっていた学者が一生かけて探求した問題、これを著者はまず、折口信夫を
「新しい国学」を樹立しようとした「国学者」として規定し(第一章 国学者折口信夫)、その上で戦前(・・第二章 『古代研究』における神)および戦後(・・第三章 戦後の折口学)の言説を、子細に検証する作業をつうじて明らかにしていく。
折口信夫は、明治維新後、廃仏毀釈による神仏分離令によって、宗教ではなく道徳体系にされた神道ではなく、あくまでも
「己自身の抱える罪や苦しみからの解放と、死者との交流という二つの側面を十分に納得させてくれる」宗教としての神道を、生涯にわたって探求を続け、思想体系として確立しようと格闘をし続けた。
折口信夫が明らかにした古代日本の神とは、
人間からみた道徳を説く神ではなく、善悪の両面を兼ね備えた、人間の意志とは関係なく、その深い情念のままに振る舞う神である。人々を祝福するだけでなく、愛欲・狡智・残虐といった正と負の両義的なエネルギーに充ち、「一挙にすべてを破壊する事のできる」ような「怒り」や「憎しみ」をもった神であった。
それは、ある意味で、
同じく民族宗教であるユダヤ教の一神教の神に限りなく近い印象すら与える「超越神」である。
折口信夫のいう「既存者」という表現は、「ありてあるもの」という旧約聖書の表現さえ想起させる。
最後の「第4章 罪、恋、そして死」において著者は、学者・折口信夫の実人生の軌跡をたどり、歌人・釋迢空として作った歌に、
一人の生きた思想家の無意識の心性の深淵まで、ともに寄り添いながら下降し、思想が発生する根源を見つめようとする。
出生の秘密に苦しみ、悩み、罪の意識を抱いて、若き日に何度も自殺未遂をした男の、罪や苦しみからの解放。そして、若き日に最愛の人を喪い、弟子であり養子でもあった一人息子を硫黄島の玉砕戦で喪った男の、死者たちとの交流・・・
国学者としての折口信夫、浄土真宗の法名でもある歌人・釋迢空、この二つの人格が交差し乖離する、ねじれた関係を凝視する著者は、思索の糸を一本一本とより分け、丹念に検証を加えてゆく。著者の論述の進め方は、詰め将棋のような執拗さというか、あるいは神経の一本一本もゆるがせにせず、慎重に手術を進めてゆく外科医の手さばきを想起させる。
韜晦(とうかい)に充ち満ちた表現をする折口信夫その人の思考をときほぐすためのアプローチは、鮮やかというよりも、粘着質なものといってもいいだろう。あるいは折口信夫が愛した探偵小説(=推理小説)のような、息の詰まるような執拗な追跡といってもいいだろうか。
折口信夫は敗戦後、弟子の岡野弘彦に、憂い顔でこう洩らしていたという。「
日本人が自分たちの負けた理由を、ただ物資の豊かさと、科学の進歩において劣っていたのだというだけで、もっと深い本質的な反省を持たないなら、五十年後の日本はきわめて危ない状態になってしまうよ」(P.263 注23)。
日本の神は敗れたもうた、という深い反省をともなう認識を抱いていた折口信夫の予言が、まさに的中していることは、あえていうまでもない。
著者は、
折口信夫がついにその生前には到達し得なかった、宗教としてみた日本の神とは何かという残された問題を、
問題を問題として認識することの重要性を指摘している。この問題は、現代に生きるわれわれ自身が考え続けなければならない問題である。
「近代の日本社会が抱える矛楯をそのままに体現していた」(P.253)折口信夫という人間存在、
その思索と生の軌跡をたどる意味がここにあるといってよいだろう。
現在もなお続く、この国の精神的な漂流状態がいったい何に起因するのか、これについて深く考えるための道標(みちしるべ)として。
<初出情報>
■bk1書評「
「いきどほり」と融合した「さびしさ」という情念を軸にすえた、折口信夫が一生かけて探求した問題の解明」投稿掲載(2010年1月20日)
<書評への付記>
「国学者」としての認識から、和歌をつくることを何よりも重視していた。学者としての折口信夫と、歌人としての釋迢空は、不可分の一体といって良い。
さて、「いきどほる心すべなし。・・」の歌は、私が初めて知ったのは大学生のときだが、非常に気に入ってそらんじていたものだ。この歌を皮切りに論を進めたこの著者の姿勢が何よりも気に入った。
この歌は、有名な「葛の花・・」で始まる14首の連作「島山」に含まれる。一般に女嫌いであったといわれている、折口信夫=釋迢空の唯一の女弟子といわれている歌人・穂積生萩(ほづみ・なまはぎ)は、宗教学者・山折哲雄との共著
『執深くあれ-折口信夫のエロス-』(小学館、1997)で次のようにいっている(P.154)
迢空の作品は、一首ずつ独立はしているが、一首だけ覗き込んではいけないようである。すべての連作は、序破急、又は起承転結に構成されている。
とにかく狙って書く人だし、自分の狙いの的を外したくない一心で、推敲もし、編集も綿密に行う人だから、一連を一幕物の演劇と思って読む方がいい。
では、連作「島山」を全首掲載しておく。沖縄での民俗調査の帰途、調査のため訪れた壱岐(いき)での連作らしい。壱岐は九州・福岡の、玄界灘に浮かぶ島である。
『海やまのあひだ』 釋迢空
大正十三年 -五十二首- 島 山
葛の花 踏みしだかれて、色あたらし。この山道を行きし人あり
谷々に、家居ちりぼひ ひそけさよ。山の木の間に息づく。われは
山岸に、昼を 地(ヂ)虫の鳴き満ちて、このしづけさに 身はつかれたり
山の際(マ)の空ひた曇る さびしさよ。四方の木(コ)むらは 音たえにけり
この島に、われを見知れる人はあらず。やすしと思ふあゆみの さびしさ
わがあとに 歩みゆるべずつゞき来る子にもの言へば、恥ぢてこたへず
ひとりある心ゆるびに、島山のさやけきに向きて、息つきにけり
ゆき行きて、ひそけさあまる山路かな。ひとろごゝろは もの言ひにけり
もの言はぬ日かさなれり。稀に言ふことばつたなく 足らふ心
いきどほる心すべなし。手にすゑて、蟹のはさみを もぎはなちたり
澤の道に、こゝだ逃げ散る蟹のむれ 踏みつぶしつゝ、心むなしもよ
いまだ わが ものに寂しむさがやまず。沖の小島にひとり遊びて
蜑(あま)の家 隣りすくなみあひみつみ、湯をたてにけり。
荒(アラ)磯のうへに
雛(ひな))の子の ひろき屋庭に出でゐるが、
夕焼けどきを過ぎて さびしも
(*カタカナは釋迢空自身による読み。ひらかなは私が補足したもの)
ちなみに「葛の花・・」の一首は、一般におもわれているような内容ではなく、匂い立つような、かなりセンシュアルでセクシュアルな意味を秘めた歌のようである。
折口信夫の「いきどほり」は、岡本太郎の「怒り」にも似て、きわめてストレートに表現されたものである。ともに、日本的「世間」への違和感の強い人だったように思われる。
阿部謹也は、「世間」から距離をとった人として、とくに
金子光晴と
永井荷風が好みのようだが、私は永井荷風は当然のことながら、
折口信夫と
岡本太郎の二人がとくに好みだ。
この二人には共通性もある。
恋人で秘書の岡本(旧姓 平野)敏子を
養女にした岡本太郎。
恋人で弟子の折口(旧姓 藤井)春洋を
養子にした折口信夫。
異性愛と同性愛という違いがあるものの、その性をめぐる関係は、日本の一般常識、すなわち「世間」から大きく逸脱していることは、否定できない事実である。宗教学者の山折哲雄風にいえば、「
脱血縁の思想」といえようか。ともに自らの血を引く子供は残さなかった、あるいは遺すことを拒否したのかもしれない。
岡本太郎が日本の学校制度に適応できず、フランスで学業を終了し長く滞在したことは、
日本を他者の眼で見る姿勢を植え付けたことはいうまでもない。
折口信夫は外遊経験はないが、自殺未遂を3度も繰り返し、学校も一度落第、大学も家業である医学を選ばず、大阪から逃げるようにして東京の國學院に学んでいる。哲学者・坂口恵が『折口信夫 霊性の思索者』9)の著者・林浩平にもらしたという、「ああ、あのひとはどうも日本人じゃないみたいですね」という表現(・・この件については
「書評『折口信夫 霊性の思索者』(林浩平、平凡社新書、2009)」参照)は、折口信夫が「世間」から距離をとって「古代」に生きてきたことの証左となろう。
「近代の日本社会が抱える矛楯をそのままに体現していた」(P.253)折口信夫という人間存在、という表現が何を意味しているかというと、神仏分離と廃仏毀釈によって、日本人の自然な宗教感情をズタズタに引き裂いてしまった、明治維新政府の"合理的な"宗教政策のことを指している。
明治政府の設計者は、西洋近代の精神的支柱となっていたキリスト教の代替物として神道(しんとう)を据えることとし、これを近代天皇制とセットになった国家神道という形に作り替え、国家神道は宗教ではない(!)としたのである。この事情については、安丸良夫の名著
『神々の明治維新-神仏分離と廃仏毀釈-』(安丸良夫、岩波新書、1979)を必読文献としてあげておく。
国家神道となった神道からは、一般民衆の宗教感情を拾い上げることは不可能となり、天理教や大本教のような新宗教である「教派神道」にゆだねられることとなった。穂積生萩の回想によれば、折口信夫は大本教には深い共感を抱いていたようだ。
折口信夫には、キリスト教徒の文芸評論家・富岡幸一郎をはじめとする、さまざまな人たちに引用される有名な述懐がある。
まさか、終戰のみじめな事實が、日々刻々に近寄つてゐようとは考へもつきませんでした。その或日、ふつと或啓示が胸に浮かんで來るやうな氣持ちがして、愕然と致しました。それはこんな話を聞いたのです。あめりかの青年達がひよつとすると、あのえるされむを囘復する爲に出來るだけの努力を費やした、十字軍における彼らの祖先の情熱をもつて、この戰爭に努力してゐるのではなからうか、と。もしさうだつたら、われわれは、この戰爭に勝ち目があるだらうかといふ、静かな反省が起こつても來ました。
(出典:『折口信夫全集 第二十巻』(中公文庫版)所収「神道の新しい方向」昭和24年 斜体部分は原文では傍線)
この話は戦争末期の昭和19年(1944年)の秋の一日、プロテスタント教会牧師の養成を目的とする東京神学大学教授となった、日本基督教団の比屋根安定(ひやごん・やすさだ)が折口信夫に頼み込んで実現した、牧師たち向けの「古事記」講義の席で耳にしたらしい。この件は、『
神道学者・折口信夫とキリスト教』(濱田辰雄、聖学院大学出版会、1995)の第二部「折口信夫の戦後神道論とキリスト教」(P.106)を参照。
「日本の神、敗れたもう」という認識をもった折口信夫の敗戦後の課題とは、神道を人間の合理的な解釈や人間からみた道徳から解放し、再び宗教としての意味づけを行うことであった。しかし、神道界では主流となることはなかったようである。
折口信夫のいう、「日本人が自分たちの負けた理由を、ただ物資の豊かさと、科学の進歩において劣っていたのだというだけで、もっと深い本質的な反省を持たないなら、五十年後の日本はきわめて危ない状態になってしまうよ」(P.263 注23)は、残念ながら実現してしまった。天皇と神道にかんする考えは異にしながらも、三島由紀夫の予言と重なるものも感じる。
しかし、最近のスピリチュアル・ブームは、神道の宗教的側面を復権するための兆しともいえるかもしれない。もちろんTV番組でのブームとは距離を置く必要はあるとは思うが、
パワースポットという英語由来の表現ではあるにしても、とくに若い女性のあいだで、神社が再び脚光を浴びるようになってきたことは、たいへん喜ばしいことである。
神社で、「二礼二拍一礼」するとき、神さまの名前はわからなくても、何かしら荘厳な、厳粛な気分になるのは、日本人の自然な宗教感情である。そこに
目に見えない超越的な存在を感じるのは、限りなく一神教に近い、といってもいいすぎではないと思われる。あるいはスピノザ的な汎神論といってもいいかもしれない。遍在する神、エーテルのように充満する神。八百万の神という表現があるが、これは「ひとつの神」を分節化された表現として捉えるべきではないか。一般的にも、私自身も、神さまの名前などまったく意識せずに、神社で礼拝している。ただ単に「神さま」として。
西行法師の有名な歌、「
何ごとのおはしますかはしらねども かたじけなさに涙こぼるる」は、まさにその超越的存在について語っているのである。
折口信夫は、大学時代から読んできた。いまあらためて再び新しい視点で読み込むことの必要を感じている。
<ブログ内関連記事>
書評 『折口信夫 独身漂流』(持田叙子、人文書院、1999)
・・「古代日本人が、海の彼方から漂う舟でやってきたという事実にまつわる集団記憶。著者の表現を借りれば、「波に揺られ、行方もさだまらない長い航海の旅の間に培われたであろう、日本人の不安のよるべない存在感覚」(P.212)。歴史以前の集団的無意識の領域にかつわるものであるといってよい。板戸一枚下は地獄、という存在不安」
書評 『折口信夫 霊性の思索者』(林浩平、平凡社新書、2009)
・・「私は大学時代から、中公文庫版で『折口信夫全集』を読み始めた。日本についてちっとも知らないのではないかという反省から、高校3年生の夏から読み始めた柳田國男とは肌合いのまったく異なる、この国学者はきわめて謎めいた、不思議な魅力に充ち満ちた存在であり続けてきた」
「神やぶれたまふ」-日米戦争の本質は「宗教戦争」でもあったとする敗戦後の折口信夫の深い反省を考えてみる
・・逆説的であるが、折口信夫のコトバのチカラそのものは激しい
「役人の一人や二人は死ぬ覚悟があるのか・・!?」(折口信夫)
(2021年11月19日発売の拙著です)
(2021年10月22日発売の拙著です)
(2020年12月18日発売の拙著です)
(2020年5月28日発売の拙著です)
(2019年4月27日発売の拙著です)
(2017年5月18日発売の拙著です)
(2012年7月3日発売の拙著です)
ケン・マネジメントのウェブサイトは
ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。
お手数ですが、クリック&ペーストでお願いします。
禁無断転載!
end























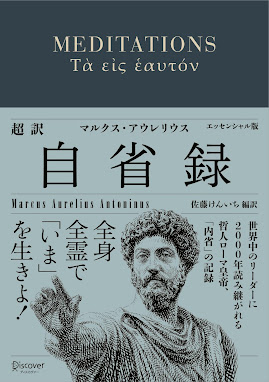


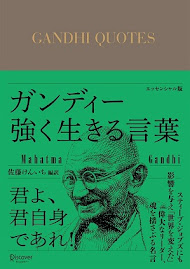











.png)






