(連合王国のユニオンジャックは構成国の組み合わせである)
英国の国民は、
EU(=欧州共同体)からの「離脱」(Leave)を選択した。
いわゆる「ブレクジット」(Brexit)である。英国(Britain)と「離脱」(Exit)の合成語であり造語である。
2016年6月23日に実施された国民投票(=レファレンダム)の結果、51.9% 対 48.1%で「離脱」派が過半数を制したのである。
まさに今日この日、ついに歴史は大きく動いたのである。「離脱か否か、それが問題だ」(To leave or not, that is the question)と優柔不断なハムレットの心境のような状態が数ヶ月に渡って続いていたが、大方の予想を覆し「離脱」という最終結論が下された。
国民投票には法的拘束力がないとはいえ、議会制民主主義(あるいは代議制)という
間接民主制では完全に反映されない「民意」が数字として表明されたのである。
悪天候にもかかわらず投票率が72%もあったということが、なによりも雄弁に物語っている。
議会制民主主義の本家本元である英国での出来事だけにより注目されるのである。
財政破綻のギリシアですら「離脱」(Grexit)をとどまったのに、
主要メンバーである英国が「離脱」を選択したのである。この意味は計り知れない大きさをもつ。「離脱」を選択した英国にとっても、「離脱」によって主要メンバーを失うEUにとっても、今回の「離脱」は EU存続にとってのターニングポイントとなる。
ドイツを制御できる大国は EU内に存在しなくなるからだ。
短期的には金融面を中心に、混乱が発生することは避けられない。英国を欧州拠点に戦略展開している日本企業にとっても、頭の痛い問題であろう。しかし、中長期的にみれば、英国国民にとってはよい選択だったと回想されることになるかもしれない。
たしかに、
物心ついてからEUに加盟していることが当たり前であった英国の若年層にとってはショッキングなことだろう。それ以外の英国とEUの関係を知らないからだ。彼らはいわゆる「ミレニアム世代」(=新千年紀世代)でもあるが、
EUにとどまるという選択は、ある意味で「現状維持」の発想であり、若年層は自分たちが思っている以上に保守的なものかもしれない。
今回の国民投票は、「離脱」支持者が高年齢層に多かったことに示されているように
「シルバー民主主義」の問題点が露呈したといえるかもしれない。だが、若年層との顕著な違いは、
EU加盟以前の英国を肌身を通じて知っていたという体験の有無である。つまりは歴史を知っているかどうかの違いだ。もちろん英国を抜本的に変身させた
「サッチャー改革」をどう評価するかという点にかんする違いもあることだろう。
(投票結果のデモグラフィック分析 BloombergBusinessWeek記事より)
だが、
英国は「島国」なのだ。大英帝国の夢よもう一度など郷愁だと解釈する人もいるがそれは当たらない。そうではなくて、
「島国」という地政学的特性をもった国家の国民がもつ「見えざる意思」、あるいは本能的なものの発露と受け取るべきではないか。
EUを実質的に仕切っているのは「大陸国家」のドイツであり、「島国」の「海洋国家」の英国にとっては不満が強かったことは容易に想像できる。
英国は、共通通貨ユーロには参加せずポンドを使いつづけてきたが、
究極の国家主権とされる通貨発行権(=シニョリッジ: seigniorage)を EU に引き渡していなかったことは幸いであった。EUを離脱するに際しても、傷口を小さくすることができるのだ。これは
ギリシアとの根本的な違いである。
逆にいえば、
ユーロを採用していなかったからこそ、英国の「離脱」は可能と考えられたのである。EUに加盟していながらユーロを使用しない国は英国のほかに、スウェーデン・デンマークといった北欧諸国がある。
すでにユーロを採用しているオランダやフランスが、仮に国民投票で「離脱」を選択しても、実行には困難をともなうことは明白だ。「離脱ドミノ」はじっさいには置きにくいと考えるべきだろう。
英国国民ではない日本国民にとっても朗報と受け取るべきインプリケーションがあると捉えるべきではないだろうか。というのも、
日本は英国と同様に「島国」だからだ。
誰が、大陸国家に牛耳られた共同体(あるいは連邦)など望むというのか?
日本に引きつけて考えれば、大陸国家・中国の北京の官僚たちに牛耳られた共同体となる。わたしなら絶対に御免被りたい。
前政権のときに浮上した「アジア共同体」なる愚かな政策構想は、今回の「英国離脱」で完全に消えたと思いたい。
日本にとって、EUは目指すべきモデルでないことは明らかだろう。
(連合王国とユニオンジャックの秘密 筆者作成)
今後、
間違いなく起こってくるのはスコットランド独立運動の再燃だろう。
イングランドとウェールズが「離脱」に傾いたのに対し、国際金融と経済の中心であるロンドンだけでなく、スコットランドと北アイルランドは「残留」を望んでいるからだ。スコットランドが独立して連合王国(UK: United Kingdom)から「離脱」となれば、
連合王国の「国の形」も変わることになる。ユニオンジャックという国旗の形も変わることになる。もしかすると、本日の国民投票の結果、「連合王国」崩壊の第一歩となった考えるべきかもしれない。
おそらく
「英連邦」(=コモンウェルス Commonwealth of Nations: 諸国民の共通の富)という英国にとっての「資産」を、どう経済面で活かすことができるかが大きな焦点になってくる。だが、経済的なパワーが喪失した場合、はたして英連邦も現在のまま推移できるかは不透明である。
また、
密接な関係にあるとされる米英関係についてだが、
EU離脱した英国が、はたして米国にとって価値あるものであり続けるかうかは不明。ドイツを牽制する役割が英国に期待されていたからだ。
より大きな観点からいえば、
「連邦離脱」が流血の事態を招かずに平和裏になされるということは、世界史においても希有な例となる。
アメリカ合州国(United States of America)から南部の11州が「離脱」を宣言したとき、「南北戦争」という武力を伴う内戦が1853年から4年間もつづき、なんと60万人(!)も戦死している。
ソビエト「連邦」(=ソ連)もまた「離脱」の危機が迫ったことにより、最終的にソ連邦が解体し、ソ連という国家は地上から消えた。1991年のことだ。そしてその直後から
ユーゴスラビア「連邦」共和国もスロヴェニアの分離独立宣言が引き金となり解体、その後の凄惨なバルカン戦争へとつながっていった。「エスニック・クレンジング」(=民族浄化)というコトバが作られた戦争のことだ。
現時点ではっきりしていることは、これから2年間のあいだに「離脱」の実務を進めるということである。「離脱」完了のあかつきには、欧州大陸内の空港、たとえば玄関口であるフランクフルト空港のイミグレーションで、
英国国民は Non-EU Citizen の列に並ぶことになる。同じ列に並ぶ日本人や米国人と共通の利害関係になるということだ。
英国のEU離脱(Brexit)で、完全に世界の政治経済の「潮目」が変わったのではないか、そんな気がしてならない。いまや、
すでに「離脱」の是非を論じる段階ではない。「賽は投げられた」のである。ルビコンを渡ってしまったのである。
すでに起こった事実は虚心坦懐に受け止め、それを外部環境変化として「与件」とし、自分の取るべきアクションに反映していかなくてはならないのである。
まだまだ不確実で不確定なことも多いが、
世界史的な出来事として捉えるべきなのだ。けっして経済だけで論じるような小さな話ではない。
そんな大きな出来事を同時代に体験できたことの意味を十分に理解すべきなのである。
<関連サイト>
Reflections on the Referendum Analysis(Stratfor, June 26, 2016)
・・「陰のCIA」の異名をもつ米国の民間情報分析機関ストラットフォーがETAとのジョイントによるマクロ経済分析論考。英国のEU離脱は、経済金融の機能不全の「結果」であって、「離脱」が原因となって発生したのではないという主張。Brexit gives it more opportunity for constructive reform and greater flexibility to deal with future regional financial and economic instability and contagion. We also argued, however, that leaving would not cure all of Britain's ills.
英国のEU離脱は、極めて合理的な判断だった 英トップエコノミストが予言していた「崩壊」 (ロジャー・ブートル :エコノミスト、東洋経済オンライン、2016年06月24日)
英国のEU離脱で何が起こるか? (みずほ総合研究所、2016年4月19日) PDfファイル
・・「離脱」決定後のEUとの交渉プロセスについて詳細に解説
英EU離脱で「英連邦」が超巨大経済圏として出現する(上久保誠人、ダイヤモンドオンライン、2016年6月21日)
・・「英国のEU離脱は、おそらく中長期的にみれば、英国にとって不利益ではない。むしろ、英国に抜けられるEUの不利益となるのではないだろうか」 日本人でもこういう見方をする人もいる。
英国の優位性は不変、EU離脱交渉でも主導権を握る(上久保誠人、ダイヤモンドオンライン、2016年7月5日)
・・「国民投票を通じて、英国の分裂が明らかになったといわれるが、筆者には、
むしろ残留派と離脱派の歩み寄りが少しずつ始まっているように見える。
国民投票がなければ、政府は新自由主義的な政策を継続し、国民はずっと不満を持ち続けることになっただろう。そして、静かに国家の分断は進行し、いつか取り返しのつかないことになったかもしれない。国民投票というプロセスを経て、英国民が学んだことは小さくない」
英国はEU離脱で「のた打ち回る」ことになる 「EU研究第一人者」北大・遠藤教授の現地レポ(東洋経済オンライン、2016年6月27日)
・・「この(イングランドの)主権的な自決意識とナショナリズムの結合は、今回の国民投票を考えるうえでも重要だと思われる。つまり、英国独立党のような、2013年までは周辺的で、その後も決して多数派を掌握できない政党ではなく、
何世紀ものあいだ主流を形成してきた保守党とその支持者にも、その2つの結合を経由して欧州懐疑主義が拡がっていった。そのことで初めて、局所的な運動を超えて、それはうねりをなしたのである」
英国が「EUを離脱しない」は本当なのか「EU研究第一人者」北大・遠藤教授が予測(東洋経済オンライン、2016年7月9日)
・・「「主権」的な議会は誰に選ばれているのか。それは国民である。その国民が、形式には諮問的であれ、総意を表明してしまった。それが国民投票である。
その直接的な意思表明は、間接的な意思決定である議会の立法や採決に対し、相当な政治的正統性を帯びる。イギリス憲法史の権威でもあるヴァーノン・ボグダノー教授はこう述べた。
「国民主権は議会主権より深い」。ほぼ間違いなく、議会は国民の声を尊重し、EU離脱に向かうだろう。
イギリスのEU離脱は経済的に合理的な選択だ(野口悠紀雄、ダイヤモンドオンライン、2016年6月30日)
・・「イギリスは世界的な金融取引の中心になっており、取引先にはオイルマネーなどもある。したがって、こうした取引について金融取引税の負担を免れることができる効果は大きいだろう。・・中略・・ ユーロに参加しなかったイギリスのほうが、概して、ユーロ圏諸国より経済パフォーマンスが良好だったのである。イギリスのEU離脱によって短期的に世界経済が混乱することは避けられない。しかしこのことと、長期的な制度選択の問題を混同してはならない。 今回のイギリス離脱の最大のポイントは、「EUという組織に重大な疑問がつきつけられた」ということなのだ。EU離脱は、イギリスという特殊な一国に限定された問題ではない」
英国の産業構造を知らずにEU離脱問題は語れない (野口悠紀雄、ダイヤモンドオンライン、2016年7月28日)
・・「イギリスの産業構造が高度サービス産業中心になっており、大陸諸国や日本のように製造業の比率がいまだに高い経済とは異なるからである。 日本では、イギリスに関して1980年頃までのイメージを持ち続けている人が多い。つまり、イギリス病から脱却できずに、経済活動が衰退しているというイメージだ。しかしイギリスは、90年代に大きく変貌したのだ。」 この点にかんしては
『イギリス近代史講義』(川北稔、講談社現代新書、2010)も参照。また次の指摘も重要。「イギリスは、アメリカと中国に対しては、貿易黒字を計上している。したがって、イギリスが貿易関係をより緊密にしたいと考える相手国は、アメリカと中国であるはずだ。・・中略・・ 日本の場合には、過去の経常収支の黒字によって海外資産が蓄積され、それを受動的に運用しているにすぎない。それに対して
イギリスの場合には、積極的に資金調達をして、それを投資に回しているのだ。つまり
国際的な資金仲介を行なっているわけだ。」 要は、国際金融立国だということだ。
EU離脱後も揺らがない、金融立国の牙城 在英28年の作家が見た、英国が世界を揺るがした日 (黒木亮、日経ビジネスオンライン、2016年7月6日)
・・「国際取引契約は英語で作られ、英国法かニューヨーク州法が準拠法で、裁判管轄はロンドンかニューヨークである。これをフランス語や英語で契約書を作り、パリやフランクフルトでの裁判を前提にすることはありえない。 また金融機関の為替取引なら金融機関同士だけでできるが、商取引、プロジェクト、M&Aなどは、法律事務所、会計事務所、保険、商品取引、海運なども関わってくる。ロンドンには多数の法律事務所、会計事務所、巨大なロイズの保険市場、世界最大のLME(ロンドン金属取引所)、バルチック海運取引を中心とする屈指の海運市場などがある。・・中略・・ 英国に来ている外国企業は金融機関に限らず、EUだけでなく、中近東とアフリカをカバーしており、EUを離脱してもこの点の重要性は変わらない。・・中略・・ 英国もEU各国も政治的に成熟した先進国で国際交渉にも慣れており、互いに妥当なところで交渉をまとめ上げるはずだ。英国は国連の常任理事国で、核の保有国でもある。28年間住んで感じるのは、そう簡単には駄目にならない英国独特の強さである。
頼りにしていた英国が!ショックを受けるフランス 英国EU残留を望んでいたフランス、英仏関係はどうなるのか(山口昌子、JBPress、 2016年6月.27日)
「政治家は市民の力を恐れるなかれ」、直接民主制の専門家が指南(スイスの直接民主制)(Swissinfo.ch、2016年6月2日)
統合は死んだ、だがEUは生きている 国家でも単なる国際機関でもない、等身大のEUとは? (遠藤 乾、東洋経済オンライン、2013年6月18日)
・・参加国にとってのメリットは、3つのP:Peace(域内平和), Prosperity(域内繁栄) and Power(域外への対抗力)。「2005年、フランスとオランダというECSC以来の原加盟国が欧州〈憲法〉条約を国民投票で葬り去り、その二年後「憲法概念は放棄」とEU首脳が明示的に合意したとき、そうした「統合」物語もまた放棄されていた」 EUは国家でも連邦でもない宙ぶらりんな存在
英国EU離脱で「欧州と世界」はどう変わるのか (遠藤乾、東洋経済オンライン、2016年7月16日)
・・「いまのドイツは戦間期のアメリカに近く、自身の権力と責任(意識)とが見合っていない状況にある。じつは、
いま欧州で必要とされるのは、責任に見合ったより一層のドイツの権力行使であり、正しい権力の使い方なのだが、「ドイツの覇権が復活した(ので警戒せねば)」とだけ述べる多くの言説は、その必要を覆い隠してしまう。こうして
中途半端なドイツの権力と責任感の下で、欧州経済社会は窒息する。そのなかで、
不満分子は当然増え、反EU機運が盛り上がる。それを担うのは、イギリス同様、グローバル化=EU統合でないがしろにされてきたと感ずる中流以下の層である。・・中略・・ 特に独仏における政党政治が底抜けすると、EUが内破するというのがボトムラインであり、それが当面ありそうにないとすると、
今回のイギリス国民投票はEU崩壊・瓦解でなく、再編をもたらすものとなろう。」
「英国国民投票-EUの反応と今後の手続きは?」(2016年6月号 質問コーナー、EUの日本語広報誌『EU MAG』記事)
・・「Q2.国民投票に先立ち、英国政府の要請で英国とEUが交渉した条件についてはどうなるのですか? A:
2016年2月18日、19日の欧州理事会(EU首脳会議)で合意された「EU内の英国の特別な地位を強化する合意(the UK Settlement)」は、消滅しました」
EUの盟主ドイツで「イギリス離脱」はどう報じられたか-これって「イジメ」じゃない? 結論が出て、ますます混迷深まる (川口マーン惠美、現代ビジネス、2016年7月1日)
英EU離脱の隠れた理由は「宗教」だ (宿輪純一、ダイヤモンドオンライン、2016年7月6日)
・・英国を英国たらしめているのは国教会(=アングリカン・チャーチ)。英国国王は国教会の首長である。英国が大陸と一線を画している理由の背景にあるものに宗教がある
イギリスEU離脱と中国の計算 (遠藤誉、2016年6月26日)
・・「イギリスがEUから離脱しても、イギリスはますます中国への経済依存度を高めるだけで、中国がEUとの距離をメルケル首相を通して強化していれば、中国は漁夫の利を得ることになる。・・中略・・ AIIB加盟に関し、イギリスに率先して手を挙げさせることによって先進7ヵ国(G7)の切り崩しを図ったわけだ。日米を除くG7のAIIB参加に成功した中国は、イギリスのEU離脱の日に備えて、イギリスとは別にEUとの連携を強化し、EUで最大の力を持っていると中国がみなしているドイツをターゲットにした。」
Brexit: The Impact on Business (Bloomberg BusinessWeek, July 29, 2016)
EU離脱もイギリス経済は全然ヤバくなってない-あの懸念は何だったのか 黄信号が灯ったのはむしろユーロ圏 (安達誠司、現代ビジネス、2016年8月25日)
・・「リーマンショック後、イギリスは先進国の中ではもっとも成長率が高い国に分類される・・中略・・ イギリスの国民投票後に、大陸欧州の銀行株が急落したことを考えると、今回の「Brexit」問題は、イギリス経済の問題というよりも、欧州の金融問題の深刻さを炙り出したと言えなくもない。このように考えると、「Brexit」の問題は、経済面でいえば、イギリスというよりも、むしろユーロ圏を中心とした大陸欧州経済の深刻さをあらためて浮き彫りにしたのではなかろうか。」
【ゼロからわかる】イギリス国民はなぜ「EU離脱」を決めたのか 露わになるグローバル化の「歪み」(笠原敏彦、現代ビジネス、2017年1月8日)
(2016年6月27日・28日・30日、7月3日・9日・24日・29日、8月27日、2017年3月18日 情報追加)
<参考情報>
「ノルウェーはなぜEUに加盟していないのですか」(ノルウェー大使館 公式ウェブサイト よくある質問 FAQ)
・・「
1994年に行なわれた国民投票の結果、ノルウェーはEUに加盟しないことを決定しました。主な理由としては、EUに加盟することによって国内および国際的政治政策で、
国としての独自性を保つことが難しいことや、貿易・産業の分野でノルウェーの利益を十分に守ることができないことなどがあげられます。ただし、
1994年の国民投票の結果をみても反対52%、賛成48%とその差は大変小さく、意見の分かれる難しい問題です。現在でも引き続き議論が行なわれています」
英国のEU離脱の衝撃は何百年と語り継がれるだろう「逆回し」で歴史をさかのぼると見えてくること(佐藤けんいち、JBPress、2017年6月6日)
・・このブログのオーナーであるわたくし自身が執筆したコラム記事。
(2017年8月15日 情報追加)
(追記) なお、2017年5月18日に出版した
拙著『ビジネスパーソンのための近現代史の読み方』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2017)では、
「想定外」であった英国の「EU離脱」と米国のトランプ大統領誕生を「2016年の衝撃」と捉えて、その衝撃を出発点とした近現代史を描いているので参照していただきたい。(2016年8月15日 記す)
<ブログ内関連記事>
■「近代」以降の英国史
書評 『大英帝国という経験 (興亡の世界史 ⑯)』(井野瀬久美惠、講談社、2007)-知的刺激に満ちた、読ませる「大英帝国史」である
・・本書には、スコットランド併合と北部アイルランド併合の歴史も詳述されている。連合王国(United Kingdom)とは、イングランドによる周辺王国の併合の結果生まれたものだ。歴史的経緯を考えれば解体もあり得る話だとわかる
書評 『大英帝国衰亡史』(中西輝政、PHP文庫、2004 初版単行本 1997)-「下り坂の衰退過程」にある日本をどうマネジメントしていくか「考えるヒント」を与えてくれる本
・・「英国に対する挑戦者としてヨーロッパ大陸から急速に勃興し英国を脅かす存在となったドイツが、何かしら日本に対して挑戦者として急速に勃興してきた中国を想起させるものがあるのだ。 歴史の教訓として、英国はドイツを意識しすぎるあまり、衰退を早めたことが本書では語られている」
映画 『マーガレット・サッチャー-鉄の女の涙-』(The Iron Lady Never Compromise)を見てきた
・・EUに懐疑的であったサッチャー首相
『2010年中流階級消失』(田中勝博、講談社、1998) - 「2010年予測本」を2010年に検証する(その1)
・・「金融ビッグバン」後の英国で、英国の証券会社に日本人として勤務していた著者が体験し、つぶさに観察した実情を「鏡」にして、日本の行く末を考察した内容の本。英国の格差社会化は、日本に先行している
書評 『イギリス近代史講義』(川北 稔、講談社現代新書、2010)-「世界システム論」と「生活史」を融合した、日本人のための大英帝国「興亡史」
・・「サッチャー革命」による金融街シティの変貌が、ジェントルマン資本主義から新自由主義への完全な移行をもたらした・・(中略)・・ 現在のシティは、すでに白洲次郎が語っていたような金融界ではない」
「近代スポーツ」からみた英国と英連邦-スポーツを広い文脈のなかで捉えてみよう!
英国については、2012年にインターネット放送で、「近代スポーツ」からみたイギリスとイギリス連邦」というテーマで語っているのでご参照いただきたい。
■EU(欧州共同体)とドイツ
書評 『ユーロ破綻-そしてドイツだけが残った-』(竹森俊平、日経プレミアシリーズ、2012)-ユーロ存続か崩壊か? すべてはドイツにかかっている
・・「
国債とは英語でいえばソブリン・ボンド(Sovereign Bond)のことだ。
ソブリンとは主権国家の「主権」を意味する。だが、
共通通貨ユーロの加盟国であるギリシアには、究極の国家主権である通貨発行権はいまやない。国家として独自の通貨はもてないのである。 にもかかわらず、
ギリシアだけでなくその他のユーロ加盟国も、財政主権など通貨発行権以外の主権を有したままの中途半端な状態になっている。これが、ユーロ設計の問題点なのだ。設計ミスといっていい」
書評 『「ドイツ帝国」が世界を破滅させる-日本人への警告-』(エマニュエル・トッド、堀茂樹訳、文春新書、2015)-歴史人口学者が大胆な表現と切り口で欧州情勢を斬る
・・すでに経済的にはドイツに従属するフランス。英国が「離脱」したあと、ドイツのさらなる巨大化は避けられないか?
■
主権在民というプリンシプルと国家主権の意味
書評 『国家債務危機-ソブリン・クライシスに、いかに対処すべきか?-』(ジャック・アタリ、林昌宏訳、作品社、2011)-公的債務問題による欧州金融危機は対岸の火事ではない!
・・
「主権国家」(ソブリン・ステート)という概念と、それを発展させてきた欧州の歴史を見ることで、現在の国民国家(ネーション・ステート)危機が、国民国家の主権者である国民にとっての危機でもある」
欧州共同体のメンバーであるということは、国家主権が制限されることを意味する。
「小国」スイスは「小国」日本のモデルとなりうるか?-スイスについて考えるために
書評 『スイス探訪-したたかなスイス人のしなやかな生き方-』(國松孝次、角川文庫、2006 単行本初版 2003)
・・「
国民投票による直接民主制を堅持するスイスには、実はプロの政治家はいっさい存在しない。みな他に職業をもっており、連邦レベルでも政治は奉仕活動」
書評 『大英帝国の異端児たち(日経プレミアシリーズ)』(越智道雄、日本経済新聞出版社、2009)-文化多元主義の多民族国家・英国のダイナミズムのカギは何か?
・・英国の強みは移民がもたらす多様性にあるのだが、度が過ぎると捉えたのが「離脱」派なのであろう
「主権在民」!-日本国憲法発布から64年目にあたる本日(2011年5月3日)に思うこと
■
「脱出」関係
「島国」の人間は「大陸」が嫌いだ!-「島国根性」には正負の両面があり、英国に学ぶべきものは多々ある
欧州に向かう難民は「エクソダス」だという認識をもつ必要がある-TIME誌の特集(2015年10月19日号)を読む
「3-11」後の個人の価値観の変化に組織は対応できていますか?-個人には「組織からの退出」というオプションもある
・・経済学者ハーシュマンの voice/exit (発言/退出)を地で行くような英国の「EU離脱」劇
(2016年6月27日・28日、7月5日・9日、2017年8月15日 情報追加)
(2020年12月18日発売の拙著です)
(2020年5月28日発売の拙著です)
(2019年4月27日発売の拙著です)
(2017年5月18日発売の拙著です)
(2012年7月3日発売の拙著です)
ケン・マネジメントのウェブサイトは
ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。
お手数ですが、クリック&ペーストでお願いします。
禁無断転載!
end























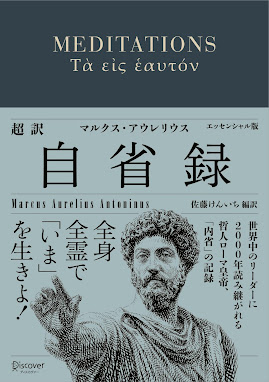


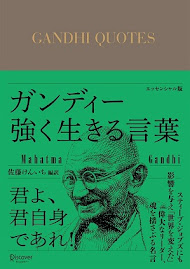











.png)






